1. ReWOOとは何か
ReWOO(Reasoning Without Observation Order)は、2023年に提案された 言語モデルの推論と外部情報参照(Observation)を分離する新しいフレームワーク です(Xu et al., 2023)。
従来の代表的アプローチである ReAct では、モデルが「Reasoning(思考)」と「Acting(外部ツール実行)」を交互に繰り返すため、各ステップで外部APIや検索を呼び出す必要がありました。これによりタスク解決の柔軟性は高い一方、
- APIコール数が多くなる(高コスト・低効率)
- 観測(Observation)が逐次的に入るため推論が不安定になる
といった課題がありました。
ReWOOは、この問題を解決するために 「推論と観測をデカップル(分離)」 する仕組みを導入しました。
- Stage 1: 推論(Reasoning)
モデルはまず、タスクを解決するために必要なサブクエリをすべて列挙し、計画を立てます。ここでは外部観測は行いません。 - Stage 2: 観測(Observation Retrieval)
Stage 1で生成されたサブクエリに基づき、外部環境から情報を並列的に取得します。 - Stage 3: 統合(Synthesis)
取得した情報をまとめ、最終回答を構成します。
論文ではこの設計を 「Plan → Retrieve → Synthesize」 と整理しており、逐次観測を繰り返すReActに比べて効率性と安定性が大幅に向上すると報告されています。
実験では、
- HotpotQA(マルチホップ質問応答)
- FEVER(事実検証)
- 2WikiMultihopQA
といったベンチマークで、ReActより少ないAPIコールで同等かそれ以上の性能を達成しました。特にマルチホップ推論では ReActの50〜70%のAPIコール数 で同等の精度を達成しました。
2. ReWOOの基本アイデア
ReWOOの核心は、推論(Reasoning)と観測(Observation)を分離し、三段階の処理フローに再構成することです。これにより、従来のReActに見られる「逐次的に観測を行う非効率性」を解消します。
2.1 Plan(推論段階)
まずモデルは 外部情報に触れずに、与えられたタスクを解くために必要なサブクエリやサブタスクを 一括生成 します。
例(HotpotQAの質問):「Q: 〇〇の出身地を答えよ」 → Plan段階で「1) 〇〇の人物情報を調べる」「2) 出身地を調べる」という2つのサブクエリを列挙。
論文では、この段階を「sketch generation」とも呼び、思考を外部環境から切り離して明示化することがポイントです。
2.2 Retrieve(観測段階)
Planで生成されたサブクエリをもとに、外部ツールやAPIをまとめて呼び出し、並列的に情報を取得します。
ReActのように「1ステップ推論 → 1回検索」ではなく、まとめて検索できるため効率が良い。
論文の実験では、この設計により APIコール数を半分以下に削減(ReAct比)できたと報告されています。
2.3 Synthesize(統合段階)
Retrieveで得られた情報をすべて統合し、最終回答を構築します
モデルは観測結果を参照しながら、Planで立てたスケッチを埋めるように推論を進めます
この構造により、逐次的に観測へ依存するReActよりも 安定した推論 が可能になります
2.4 ReActとの違い
ReAct:ReasoningとObservationを交互に実行(逐次的)。柔軟だが非効率で不安定
ReWOO:Reasoning(Plan)を先にまとめて行い、その後でObservationを並列的に取得 → 最後に統合
結果、ReWOOは 効率性(少ないAPIコール) と 安定性(推論の一貫性) を両立します。
3. アルゴリズムの流れ
ReWOOの処理は、Plan → Retrieve → Synthesize の三段階で進みます。
論文では、このフレームワークを HotpotQA や FEVER などのマルチホップ質問応答タスクに適用し、ReActよりも少ないAPIコールで同等以上の精度を実現しました(p.6–7)。
以下に、HotpotQAを題材とした具体的な流れを示します。
ステップ1:Plan(サブクエリ生成)
- 入力: 「『Gravity’s Rainbow』を書いた作家の国籍は?」
- モデルはまず、外部検索を行わずに必要なサブクエリを生成する
- 「Gravity’s Rainbow の作者を特定する」
- 「その作者の国籍を調べる」
- この段階は純粋に推論だけで行われ、Observationは伴わない
ステップ2:Retrieve(外部観測)
- Planで得られたサブクエリを外部ツールに投げ、情報を並列的に取得する
- クエリ1 → 「Gravity’s Rainbow の作者は Thomas Pynchon」
- クエリ2 → 「Thomas Pynchon の国籍はアメリカ」
- ReActのように逐次呼び出すのではなく、まとめて観測を実行できるのが特徴
ステップ3:Synthesize(統合)
- モデルは観測結果を取り込み、最終回答を構築する
- 出力: 「『Gravity’s Rainbow』の作者 Thomas Pynchon はアメリカ国籍である」
実験結果
- HotpotQA:ReActと同等の正答率を維持しつつ、APIコール数は 約50%削減
- FEVER:観測数削減により効率性が向上しつつ、幻覚の発生率が低下
- 2WikiMultihopQA:複数サブクエリを並列処理するReWOOが有効に機能
4. LangGraphでの実装例
coming soon…
5. 利点と課題
5.1 利点
- 効率性の向上
- ReActでは「推論 → 観測 → 推論 → 観測…」を逐次繰り返すため、外部APIの呼び出し回数が多くなる
- ReWOOは「Plan → Retrieve → Synthesize」によって観測をまとめて実行できるため、APIコール数を大幅に削減できる
- 実験(HotpotQA, FEVER)では、ReAct比で約50%のAPIコール削減を達成
- 安定した推論
- 観測を逐次挟まないため、モデルが部分的な観測に引きずられるリスクが減る
- Plan段階で推論の全体構造を固めるので、一貫性のある答えを導きやすい
- 並列処理の活用
- 複数のサブクエリを同時に投げられるため、外部検索・API呼び出しを効率化できる
- 実際に 2WikiMultihopQA のようなマルチホップタスクで有効性が確認されている
- 幻覚の抑制
- 観測情報を一括で取得 → 推論に組み込むため、根拠のない回答を生成する頻度が低下
- FEVER(事実検証)では、ReActよりも幻覚率が低いと報告
5.2 課題
- 初期プランニングの品質依存
- Plan段階で十分なサブクエリを立てられなければ、Retrieveで必要情報を取り逃す可能性がある
- 論文でも「Planの質が低いと、全体性能が下がる」点が指摘されている
- 柔軟性の欠如
- ReActのように「観測結果を見て即座に計画を修正する」ことは難しい
- 想定外の観測結果に遭遇した場合の適応力は、逐次型のReActに劣る
- 長期タスクへの適用性
- 非常に多段階の推論では、Planで膨大なサブクエリを生成する必要があり、コンテキスト長や効率の面で制約が出る
- 論文でも「long-horizon reasoning」は今後の課題として言及
- 実装上の制約
- 並列でObservationを取得できる環境(APIやデータベース)が必要
- 社内システムへの適用では、既存のAPI設計が並列呼び出しに対応していないと効果を十分に得られない
まとめ
ReWOOは、ReActの逐次観測に伴う非効率さを克服し、効率性・安定性・幻覚抑制に強みを持つ手法です。
一方で、Plan段階の品質依存・柔軟性不足・長期タスク対応が課題であり、論文でも「今後の研究テーマ」とされています。

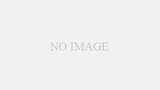
コメント